
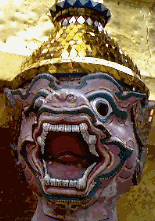 トップページに戻る
トップページに戻る
第1部 落書き解説

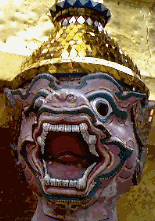 トップページに戻る
トップページに戻る
第1部 落書き解説
第2部 ラマキエン解説
各面の紹介「エメラルド寺詣り」にすすむ![]()
第1部 落書き解説
![]()
壁画をじっくり見てみますと、ストーリーとは別に、画面のあちこちにタイの風俗が書かれているのに気づきます。ここで翻訳に使わせてもらった本にもあらかたは印刷されていますが、中にはカットされている部分もあります。80面のウサギとカメの落書きを見た時には思わず微笑んでしまったのですが、この本では旗の先だけがわずかに見えているだけです。
まずはこの落書きの一覧表(まだまだ抜けているとは思うけど)を紹介します。
落書き紹介にすすむ トップページに戻る![]()
第2部 ラマキエン解説
![]()
以下を読まずに
各面の紹介「エメラルド寺詣り」にすすむ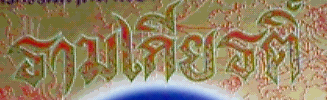
タイではみやげ物のお猿とか悪魔の図柄を町でよく見かけます。
これはワット・プラケオの壁画を模した者が多いのですが、図柄そのものは、タイの(というより東南アジア全体の)古典文学ラマキエンのイラストなのです。
この物語発祥の地インドや東南アジア各国ではラーマーヤナと称していますが、タイではラマキエンという名前で呼ばれています。
そこでラマキエンとはどんなストーリーなのか知りたいと思い始めたのです。
何人かのタイ人に聞いてみたのですが、誰でも知っている物語というものの、日本人が忠臣蔵を知っているのと同様で、主な登場人物名や有名なエピソードを知っていると言うだけで、詳細にわたっては、あんまり知らないのかなと思うようになりました
そこで本屋に行って見てみたのですが、最初はなかなか見つからず、まとまったものも見当たらなかったのですが、長年本屋あさりを続けていると結構収集できました。
まず、最初に見つけたのが、タイ語の説明の下に英語でも書いてあるうすっぺらな本で、これはハードカバーの本とほんとにペラペラの本と2種類あったのですが、お金の関係からペラペラの方を購入したのです。でもこの本いくつか問題があって、最初に買った数冊には英語の翻訳も書いてあったのですが、あとから買った物にはタイ語だけしか書いていないものがあり、結局、順番に絵をながめるだけということになってしまったのです。また、この本は、たくさんの分冊になっており(途中で解ったのですが全34冊)番号が明確に振られていないし、タイ語でしかタイトルが書いてない(多分、XXの巻と書いてある)ので、前に買ったかどうかの確認が非常に時間がかかったこと−表紙の色とISBN番号だけで重複を避けるように努力したのです。そのおかげで重複はなしで、20冊くらい購入できたのです。その後、セット販売されていたのを見つけて、買って帰ったのですが、ヌケがあったりして、50冊くらいあるのだけれど、未だに全冊揃っていないのはけったくそが悪いのです。
次は6冊セット、その次は登場人物のイラスト集、子供むけの本数冊、またまた登場人物のイラスト集、いったいいくら買えば気が済むのだというくらいあります。そして、やっとめぐりあえた英語版の全訳本、これはしっかりしています。色々な解説も出典も書いてありますのでタイ語が読めない人にとっては、最もよく解る本だと思います。でも読んでみると退屈です。お便所に置いておき、朝起き抜けに眠い目をこすりながら読んでいたのですが、なかなか進みません
日本語の本では、ラーマーヤナを2種類見つけました。子供向けの本と平凡社の東洋文庫とです。子供向けの本といってもあんまり面白いと感じませんでした。私は変人で、人が面白くないものでも意外に面白がる性格ですから、この本を結構楽しんで読んだのですが、普通の人にはきっと退屈な本だと思います。そして、平凡社のほうはというと、7冊セットの予定が2冊しか発行されておらず、詳細の翻訳なのですが、やはり退屈でもあります。
それで、物語はだいたい理解できたのですが、ワット・プラケオの壁画はどんな内容かという事がなかなか分からなかったのですが、その後見つけた、英語とフランス語とタイ語で書かれた美術書(壁画の解説書)で一挙に解決したのです。この本の解説の部分とかは無視しているので、正しいかどうかは知れませんが、おのおのの場面の解説が、それほどたくさん書いてないので、もともと壁画の横に書いてある説明のような気もしています。ここでは、その内容について著作権を無視して勝手に翻訳しました。ただ直訳では翻訳の拙さが目立ちますので、上方落語の「天王寺詣り」風にアレンジしたものを掲示します。
各面の紹介「エメラルド寺詣り」にすすむ トップページに戻る 最初に戻る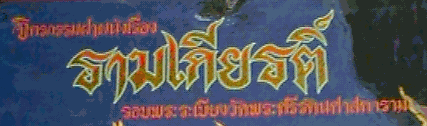
THE RAMAKIEN
MURAL PAINTINGS ALONG THE GALLERIES
OF THE TEMPLE OF THE EMERALD BUDDA
Third Published 1995
First Published 1981
![]()